知って安心!仮想通貨で得た収益から雑所得・税金の計算方法 -「移動平均法」と「総平均法」
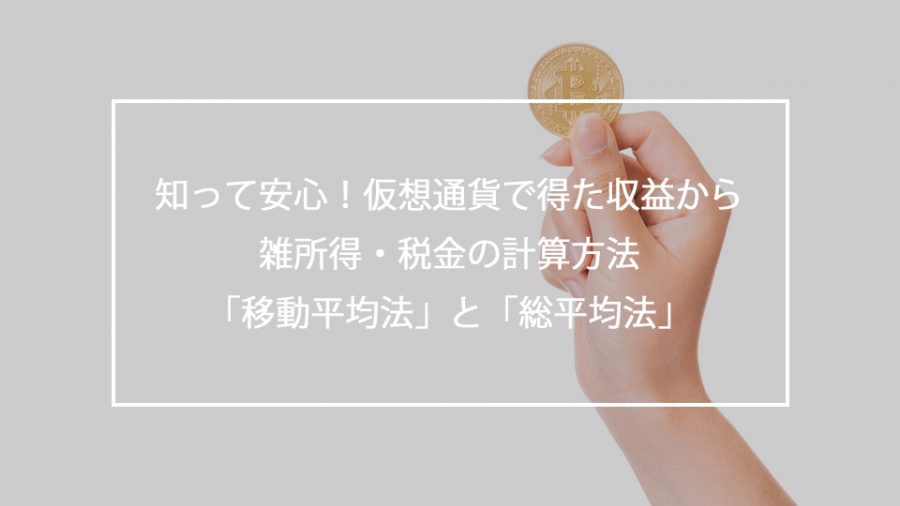
仮想通貨の計算の話に入る前に、イメージがしやすいと思いますので、仮想通貨よりももっと身近な話から入りたいと思います。
私たちが住む自由経済の社会では、モノの値段は日々変わっています。
ガソリンスタンドでは毎週ガソリンの値段が変わります。主婦の方であれば、野菜が高い、安いという価格変動を実感されているかもしれません。
消費者の立場であれば、実感はあっても、このような値段の変動をいちいち帳簿につけている人はいないでしょう。
ところが、ひとたび自営業者や企業の立場となるとしっかりと値段を帳簿につけて管理していく必要があります。
今回のテーマは、消費者としてではなく、ガソリンスタンドやスーパーのお店側の立場をイメージして頂くことが、最初のステップです。
実は、仮想通貨の投資家も自営業者や企業と同じ立場に立っているのです。
前の記事はこちら→どの時点で利益は決まる?仮想通貨で税金が決まる利確タイミングとは

仮想通貨で得た収益から雑所得・税金の計算方法 -「移動平均法」と「総平均法」
例:コーヒー屋さんで例えた場合
単純な設例
まず肩慣らしとして、コーヒー屋さんの例で考えてみましょう。このコーヒー屋さんはいくつかの豆の種類を扱っていますが、今回はアラビカ豆について考えてみましょう。
設例1
- 4月にアラビカ豆を@1,000円で1キロ仕入れた。
- 5月に同じアラビカ豆を@1,200円で1キロ仕入れた。
- 6月にアラビカ豆を@2,000円で1キロ販売した。
- 年度末に、棚卸しをしてみると1キロ分のアラビカ豆が売れ残っていた。
- このコーヒー屋さんの1年間のアラビカ豆の利益はいくらか?
ここから先を読み進める前に、ぜひ、上記1の設例の答えをご自身で結論を出してみてください。
先入先出法(さきいれさきだしほう)
@マークは前回出てきたように単価を表すマークでしたね。設例1では1キロ当たりの単価を示しています。
まず、このような計算をする人がいるかもしれません。
- 6月売価2,000円 - 4月仕入 1,000円 = 利益 1,000円
このような計算方法を「先入先出法」と言います。
先に仕入れたものから払い出したと考える方法です。直観的にはイメージしやすいかもしれません。
後入先出法(あといれさきだしほう)
一方で、次のように計算する人もいるでしょう。
- 6月売価2,000円 - 5月仕入 1,200円 = 利益 800円
このような計算方法を「後入先出法」と言います。
後(5月)に仕入れた方から払い出すから、「後入れ先出し」です。そのままの表現ですね。
平均法
いやいや、次のように計算する人もいます。
- 6月売価2,000円 -(4月仕入1,000円 + 5月仕入1,200円)÷2 = 利益900円
このような計算方法を「平均法」と言います。
一体どの計算方法が正しいの?
設例1のアラビカ豆の利益についてまとめてみましょう。
- 先入先出法 利益1,000円
- 後入先出法 利益 800円
- 平均法 利益 900円
という3つの結果が出てきました。
理屈の上ではどの計算方法も正しそうです。
ところが明らかに使ってはならない方法があります。それは「後入先出法」です。国際基準との整合性から日本では「後入先出法」が使用禁止となったのですが、アメリカでは現在でも使用されています。
有名な仮想通貨税金計算アプリの中には、この「後入先出法」を選択可能なものがあります。日本の投資家が「後入先出法」を使用することはできませんので注意しましょう。
次に、「先入先出法」ですが、「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」という国税庁の文書には「平均法」での例示が示されておりますので、個人投資家が仮想通貨の計算を行う場合には「平均法」で計算するのが望ましいものと考えられます。
もし、コーヒー屋さんのアラビカ豆を仮想通貨に置きなおして考えるのであれば、「平均法の利益900円」が正解になります。
「払出単価の計算方法」
さきほど見たような「先入先出法」や「平均法」などの計算方法のことを「払出単価の計算方法」と呼びます。
仮想通貨を離れて現実のビジネスでもこのような計算は当たり前に行われています。
読者のみなさんの所属する会社が同じ材料や商品を数多く扱う業種の場合には、上で見たいずれかの「払出単価の計算方法」を選択しているはずです。考え方を知っておいて損はないでしょう。
移動平均と総平均法
「平均法」とは
「平均法」は「移動平均」と「総平均法」をあわせた表現と考えればよいでしょう。違いは設例を見ていけばすぐに理解できるはずです。
2017年のビットコイン市場を振り返る
設例2
個人投資家Uさんは2017年以下のような取引を行った。Uさんの獲得した利益はいくらか。(BTCはビットコインの略称です)
- 4月 BTC 1枚購入@50,000円
- 5月 BTC 1枚購入@130,000円
- 8月 BTC 2枚売却@530,000円
- 11月 BTC 1枚購入@1,200,000円
さきほどの設例1と同じように、ご自身で一度Uさんの2017年の利益がいくらか考えて結論を出してから読み進めてください。
移動平均法
2017年はいま振り返ってみても恐ろしいほどの上昇相場だったことがわかります。
Uさんの立場になって考えてみればこのようになると思います。
4月に1枚ビットコインを購入してみた(@50,000)。まだまだ上昇すると思い5月にもう1枚購入した。(@130,000)。
平均購入単価 @90,000 =(4月購入@50,000+5月購入@130,000)÷2枚
8月に購入単価の何倍にもなったので利食いすることにした。
(8月売価@530,000円-平均購入単価@90,000円)×2 = 2017年利益880,000円
8月に利益確定した分もあるし、11月にさらなる上昇を期待して@1,200,000でBTCを1枚購入した。この1枚は2018年に持ち越す(@1,200,000円)。
投資家の心理に沿って考えると、2017年の利益は880,000円となりそうです。
総平均
しかし、次のように考えることもできます。
1年間全部の仮想通貨の購入単価を平均するのです。
(4月購入@50,000円+5月購入@130,000円+11月購入1,200,000円)÷3枚
=総平均単価@460,000円
(8月売価 530,000円 -@総平均単価@460,000)×2枚= 2017年利益140,000円
2017年の利益は140,000円となり、2018年に繰り越す1枚のBTCの単価は@460,000円です。
移動平均と総平均まとめ
まとめましょう。
- 移動平均法による2017年の利益 880,000円
- 総平均法による2017年の利益 140,000円
とても大きな違いになりました。
総平均法は間違いでしょうか?いいえ、そんなことはりません。
国税庁の文書にもしっかり総平均法でよいと書いてあります。
「同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)。」(3ページ)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
2017年のビットコインのように急激な変動があり、かつ取引枚数が少ない場合、設例2でみたような極端な結果になります。
仮想通貨を離れて、一般のビジネスの取引では、取引件数が多く、購入と売却が頻繁に行われるときは、「移動平均法」を使っても「総平均法」を使ってもさほど多くの差がでないと言われています。このため「移動平均」でも「総平均」でもどちらでもよい、と国税庁は判断したものと考えられます。
「移動平均法」と「総平均法」の差はどこにいったのか?2018年を考える。
2017年の、「移動平均法」での利益が880,000円、「総平均法」での利益が140,000円でした。この差がどこへ行ってしまったのか、という問題がまだ残っています。
その答えは2018年の取引を考えれば分かります。
設例3
個人投資家Uさんは、2018年3月にビットコインの残りの1枚を900,000円で売却した。2018年の取引は以上であった。移動平均法、総平均法それぞれの2018年の利益の金額はいくらか。
ただし、繰り越したビットコインの単価は以下のとおりであった。
移動平均法の繰越単価@1,200,000円(2017年11月購入分)
総平均法の繰越単価@460,000円(2017年4月、5月、11月購入分の総平均)
答えは
移動平均法 2018年3月売価@900,000 -2017年11月購入@1,200,000=2018年利益△300,000円(=300,000円の損失)
移動平均法 2018年3月売価@900,000 - 2017年総平均単価@460,000円=2018年利益 440,000円
試しに2017年と2018年を合計してみましょう。
- 移動平均法:2017年利益880,000円 +2018年利益△300,000円=580,000円
- 総平均法:2017年利益140,000円+2018年利益440,000=580,000円
となります。
結局、2年間の合計利益は、移動平均法を使用しても、総平均法を使用しても、同じ580,000円になるのです。1年目の利益の差は2年目以降で調整されるだけなのです。
「移動平均法」「総平均法」の全体まとめ
2年間を合計してみれば同じ利益になりますが、税金計算はそうはいきません。税金は1年単位で計算して納めることが法律で決まっているからです。
移動平均法の場合
1年目に880,000円について課税されます。2年目の300,000円の損失については他の仮想通貨で利益が出ていない場合には切り捨てられるケースが多いでしょう。300,000円の損失が切り捨てられた場合の課税対象は880,000円となります。
総平均法の場合
一方で、「総平均法」の場合は、1年目に140,000円、2年目440,000円の合計580,000円が課税対象となります。
ざっくりいえば「移動平均法」を選択した場合には880,000円分の利益について税金を払い、「総平均法」を選択した場合には580,000円の利益について税金を払うことになります。
筆者が助言するならば、仮想通貨の確定申告の初年度は利益が小さく出る方法を選択するよう助言すると思います。先に税金を払って良いことはあまりないからです。(ただし、個別事情による例外はあります。)
「移動平均法」「総平均法」の選択は、恣意的な利益操作を排除するために、一度選択した計算方法は継続適用しなければなりません。事前によくシミュレーションを行って慎重に選択するようにしましょう。
iDeCo・ふるさと納税・仮想通貨の申告に対応、個人事業主・会社員の副業でも使えるおすすめ会計ソフト
-
個人事業主の銀行口座・屋号(開閉)
-
請求書未経験者のための作り方・送付方法(開閉)
-
個人事業主の節税(開閉)
-
ふるさと納税(開閉)
-
仮想通貨の確定申告(税理士執筆)(開閉)
-
e-tax(電子申告)について(開閉)
-
クラウド会計ソフトfreeeについて(開閉)
-
フリーランスと保育園(開閉)



