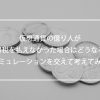仮想通貨の確定申告後に税金を支払うタイミングと所得税の納付方法をまとめました!
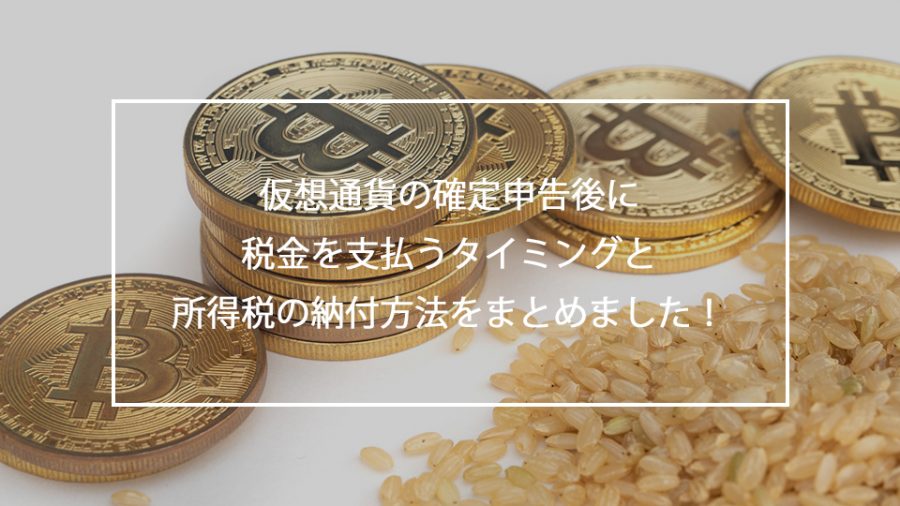
まず最も大事な納付期限について確認していきましょう。
納付期限が大事なのは、期限を過ぎてしまうと、もともと納付しなければならない所得税とは別に「延滞税」が課されてしまうからです。
前の記事はこちら→仮想通貨の確定申告を楽にしてくれる6つの税金計算ツールで出来る機能の一覧と詳細

仮想通貨の確定申告後に税金を支払うタイミングと所得税の納付方法
Ⅰ.所得税の納付
1.通常の納付期限
確定申告に伴う所得税の納付は、原則、確定申告の期限と同じ3月15日となります。確定申告の期限と同時に「納付期限が3月15日」であることは、ぜひ覚えておきましょう。
サラリーマンなど普段確定申告に馴染みのない方は、確定申告書の作成を3月15日ギリギリまで引っ張ってしまい、納税資金のことまで頭が回らない場合もあるかもしれません。
確定申告の作業を早めに進めておくことも大事なことです。
2.「納付書」で納付する。
最も一般的な納付方法について確認していきましょう。
所得税の確定申告を行うと、自動的に税務署から「納付書」が送られてくるわけではありません。自分で「納付書」という書類を書いて、金融機関で税金を納付します。
国民健康保険税や国民年金のように納付書が自宅に届くわけではないので注意しましょう。
「確定申告書」を印刷して税務署に持参したり、電子申告を行ったが、別途、紙で提出しなければならない書類がある場合には、税務署で配布している「納付書」を必ず貰って帰りましょう。
電子申告を行っていて、税務署に出向く必要がない人は、近くの銀行や郵便局に「納付書」を置いていないか聞いてみましょう。利用者の利便性向上のために「納付書」を置いているケースが多いです。
もし、お近くの金融機関にも納付書を置いていないという場合は、税務署に郵送してもらうことができます。この場合は往復の切手代がかかってしまいます。
3.「納付書」の書き方
納付書の書き方ですが、納付書の記入例があります。記入例を見ながら作成しましょう。最初は慣れないかもしれませんが、記入例の通り書ければ、ちゃんと金融機関の窓口で受け取ってくれます。
納付書の記入例はこちらです。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/pdf/24100038-1.pdf
4.振替納税
「振替納税」とは、事前に税務署と金融機関に「依頼書」を提出することにより、自動的に銀行口座から税金が引き落とされる仕組みです。
水道料金や電気代などを銀行口座から「自動で引き落とす」仕組みを利用されている方もいらっしゃると思いますが、あれと同じと考えれば良いでしょう。
一度申し込んでおくと、次回以降も税金を引き落としくれます。毎年確定申告を行う自営業者やフリーランサーの方は申し込んでおくと便利でしょう。
5.振替納税のちょっとした裏技?
この「振替納税」はちょっとした裏技のような使い方があります。3月15日に納付が間に合いそうもない場合、3月15日までにこの「振替納税」の「依頼書」を提出しておくのです。そうすると延滞税がかからず、納付を4月20日まで伸ばすことができます。
仮想通貨でたまたま大きな利益が出てしまい、3月15日までに納税資金の準備が間に合わないという人は「振替納税」を申し込んで、納付を少し先送りできます。
翌年以降は税務署に連絡することで「振替納税」をキャンセルしたり、「自動引き落とし」する銀行口座を変更することもできます。
「振替納税」の情報はこちらです。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm
6.ダイレクト納付
「ダイレクト納付」とは、e-taxを利用して確定申告を行った後、電子納税をする手続きのことです。
- 税金の納付が自宅で可能となり、金融機関での待ち時間がない。
- 期日を指定して税金の納付ができる。
- インターネットバンキングの申し込みは不要。
ということで、ついにここまで便利になったか、と大いに期待された「ダイレクト納付」でしたが、よくよく調べてみると、デメリットがありました。
特に気になったのは次のふたつです。
- 「ダイレクト納付利用届出書」を提出してから利用開始まで1か月程度かかる。
- 利用できる金融機関が限られている。
特に、楽天銀行、住信SBIネット銀行、ジャパンネット銀行といった主要なネット銀行が「ダイレクト納付」には対応しておらず、筆者はがっかりしました。
対応している金融機関を利用している人や、頻繁に税金の納付があるという人は「ダイレクト納付」を利用するのも良いでしょう。
「ダイレクト納付」に対応している金融機関は次のリンクに記載されています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100030/kinyu.htm
一度申し込んだ「ダイレクト納付」は「ダイレクト納付解約届出書」を提出することで取りやめることもできます。
7.インターネットバンキング等による電子納税
「インターネットバンキング等による電子納税」という納付方法もあります。
一見すると「ダイレクト納付」と似ていますが、こちらはその名の通り、インターネットバンキングが必要となる納付方法です。
e-taxで申告を済ませた後、e-taxのメッセージボックスから「納付区分」番号を取得し、「ペイジー」の機能を使って税金を納付します。
e-taxで登録した「利用者識別番号」「納税用確認番号」がそのままペイジーの入力項目になります。e-taxの登録情報は納税にも使用するのでしっかりと保存しておきましょう。
自営業者・フリーランサーにとっては、「振替納税」か、この「インターネットバンキング等による電子納税」が便利だと思います。
8.クレジットカード納付
クレジットカード納付は、「インターネットバンキング等による電子納税」と流れは一緒で、e-taxでの申告の後、手続きが分岐するだけです。
インターネットバンキングで納税する人はネットバンキングの画面に移動して手続きをしますが、「クレジットカード納付」をしたい人は、「クレジットカード納付」用の画面に移動します。
「クレジットカード納付」の画面はこちらです。
「クレジットカード納付」にはデメリットがあって、手数料が発生してしまうことがあげられます。
手数料の金額については、上記の「国税クレジットカードお支払サイト」でシミュレーションできますので、事前に手数料をシミュレーションしてから利用したほうが良いでしょう。
一方で「クレジットカード納付」を利用するメリットもあります。クレジットカードの引き落とし日まで税金の納付を先延ばしできるメリットがあるのです。
具体的には、3月15日までに「国税クレジットカードお支払サイト」で手続きさえしてしまえば、クレジットカードの引き落としが、3月15日以降になっても延滞税はかからないのです。
「手数料」と「口座から税金が引落されるまでの時間」をどのように考えるかは人によると思います。
筆者は税金を払うのに、さらに加えて手数料を払うという考えが好きになれず、「クレジットカード納付」はあまりおすすめしていません。
9.所得税の納付方法のまとめ
税金の納付方法はたくさん用意されていて長くなってしまいましたので、もう一度まとめておきます。
- ①納付書による納付
納付書(紙)を記入して金融機関で納付する方法です。最も基本的な納付方法です。 - ②振替納税
「自動引き落とし」による納税方法です。銀行口座から4月に税金が引き落とされます。 - ③ダイレクト納付
新しい税金の納付方法で納付日を指定できますが、申し込みに1か月ほどかかります。 - ④インターネットバンキングによる納税
いわゆるペイジーを利用した納付方法です。 - ⑤クレジットカード納付
手数料はかかりますが、クレジットカードを使用して税金を納付する方法です。
筆者の感覚では、サラリーマンの方であれば①で十分だと思います。自営業者・フリーランサーの方であれば、②か④がよいのではないかと思います。
Ⅱ 住民税の納付
次に住民税の納付方法を確認しておきましょう。
1.「普通徴収」と「特別徴収」 その違いとは?
確定申告の第二表に「住民税に関する事項」を見てみましょう。
「住民税に関する事項」に「給与から差し引き」「自分で納付」の選択があり、どちらかを〇を付けることになっています。
特別徴収
「給与から差し引き」のことを「特別徴収」と呼びます。「特別徴収」を選択した場合には、会社のお給料から仮想通貨に関する税金もあわせて天引きされることになります。
普通徴収
もう一方の「自分で納付」のことを「普通徴収」と呼びます。
「普通徴収」の場合は、仮想通貨に関する税金分だけを、自分で納付する方法です。
給料に関する住民税は給料から天引き、仮想通貨に関する税金は給料とは別に自分で納付するのが「普通徴収」です。
会社には仮想通貨に関する所得の情報が行きませんので、「自分で納付」(普通徴収)を選択する方を筆者はおすすめします。
2.「普通徴収」による税金の納付方法
「普通徴収」を選択すると、納付書が自宅に送られてきます。
納付は年4回に分けて納付しますが、一度に納付してしまってもかまいません。
通常は納付書を金融機関に持参して納付することが多いと思いますが、納付書がペイジーに対応している場合には、ATMやインターネットバンキングで納付することができます。
以上が、確定申告後に税金を納める方法と流れになります。仮想通貨で利益をあげていると確定申告自体に目が行ってしまいがちですが、税金のことも忘れずに頭に入れておくようにしましょう。
iDeCo・ふるさと納税・仮想通貨の申告に対応、個人事業主・会社員の副業でも使えるおすすめ会計ソフト
-
個人事業主の銀行口座・屋号(開閉)
-
請求書未経験者のための作り方・送付方法(開閉)
-
個人事業主の節税(開閉)
-
ふるさと納税(開閉)
-
仮想通貨の確定申告(税理士執筆)(開閉)
-
e-tax(電子申告)について(開閉)
-
クラウド会計ソフトfreeeについて(開閉)
-
フリーランスと保育園(開閉)