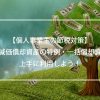税理士に支払った費用(顧問料)は節税になるのか、節税以外のメリットも?【個人事業主の節税対策】
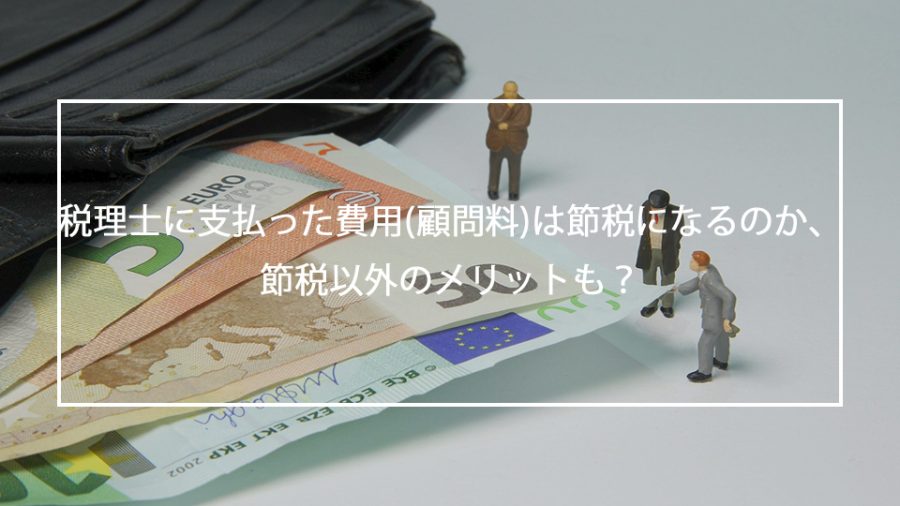
個人事業主であっても、事業がある程度発展してきた段階や創業前後からのお付き合いで税理士さんに関与していただいているケースは珍しくありません。
税理士さんに経理面を面倒見ていただくと毎月の経理処理から年度末の確定申告に至るまで、非常に助かるものです。その反面、費用がかかるのは致し方ないところ。
今回はこの税理士費用(顧問料)が節税になるのかどうか、また節税かどうか以外にメリットがあるのかどうか、について見てみましょう。

税理士に支払った費用(顧問料)は節税になるのか、節税以外のメリットも?
税理士に払った顧問料って経費になる?
顧問税理士と契約をすると、毎月数万円~数十万円の費用が発生します。これは業務に関する支出なので、経費として計上することができます。
経費として計上できるということは、節税効果があるということは前回までの記事で既に何度か確認済ですね。
一般的には税理士と顧問契約をすると、税理士さんから月ごとに日計表の集計をしてもらうことになります。
この際、月額で費用を支払うことになり、これを「税理士顧問料」といいます。
税理士顧問料の相場は、企業の売り上げに応じて上がっていくことがほとんどです。
個人事業主の年間売上が1,000万円~2,000万円の場合、月額顧問料は2万~3万円程度です。以降、年間売上に応じて顧問料も上がっていきます。
税理士顧問料の節税以外の効果
税理士に顧問料を支払って、事業の経理を面倒見てもらうことは経費になる、つまり節税になるのですがそれ以外にも大きなメリットが2つあります。
- 税理士の眼を通すことで、適正な経理処理をできることから節税効果が最大化される
- 広くビジネスを知る税理士から見た、経営上のアドバイスを受けることができる
- 万が一の税務調査に関するリスクが軽減される
- それぞれもう少し詳しく見てみましょう
税理士の眼を通すことで、適正な経理処理をできることから節税効果が最大化される
税理士と顧問契約をすると事業の経理処理を面倒見てもらえるわけですから、顧問料以外にも全ての収支について適切な会計処理がなされているかが厳しくチェックされます。
顧問税理士からは費用計上し忘れている経費についてもアドバイスされるのが一般的ですし、その逆に費用計上できない支出についても認められません。
適正な経理処理を追求していけば節税効果が高まることはこれまでの記事でもご紹介してきましたが、経理処理を専門家に診てもらえるというのが最大のメリットです。
広くビジネスを知る税理士から見た、経営上のアドバイスを受けることができる
税理士というポジションは特に強い税法の専門分野がそれぞれにあります。とはいえ、あらゆる分野の経営について経理処理の面から関与している仕事です。
税理士同士での情報交換もありますし、なにより顧問先事業者の生の情報を常に追いかけている立場です。ビジネスについて高い視点から分析・指導することが可能です。
顧問税理士からは、ちょっとしたビジネス上のアドバイスを常に受けることができるでしょう。これは孤独な個人事業主にとっては非常にありがたい存在といえます。
万が一の税務調査に関するリスクが軽減される
個人事業主が経理業務上で最も恐れているケースの1つが、税務署からの税務調査です。
税務署内部関係者でなければどういった根拠で税務調査が実施されるかが分からないのが怖いところですが、税理士に顧問料を支払って面倒みてもらうことでこのリスクは減ります。
まず税務署へ提出する確定申告書そのものが税理士の眼を通した適切なものになりますから単純に税務署から見て疑問点があるものになりにくいという構図があります。
それでもなお税務調査対象となった場合にも個人事業主がすべてを答えるわけではなくなります。特に解釈の部分は顧問税理士の出番になることでしょう。
日々の業務で税務調査を過度に心配しないで済むのは、税理士を雇う隠れたメリットです。
税理士への顧問料、源泉徴収の処理について
税理士に顧問料を支払うときは、どのように仕訳(会計処理)をすれば良いのでしょうか?
ちょっと難しいのは「源泉徴収が必要なケース」になりますがそれほど複雑ではありません。
顧問料に源泉徴収が必要なケースとは原則として、税理士顧問料の支払先が「個人」の場合です。「法人」の場合は不要です。
税理士事務所とお付き合いがないうちはちょっと判りにくいのですが、税理士事務所にも個人経営の事務所と税理士法人の事務所があるのです。
これとは別で税理士側だけでなく個人事業主側の事情も源泉徴収の有無に関わってきます。
個人事業主が税理士を雇う場合、以下の2つの条件を満たす場合には源泉徴収が不要になります。
- 従業員を雇用していない
- 給与支払事務所等の開設届出書の提出を行なっていない
税理士側の事情、事業主側の事情それぞれを照らし合わせて顧問料に源泉徴収が必要になるかどうかを確かめておく必要があります。
税理士への顧問料の源泉徴収額の計算方法と納付手続きの手順
税理士の源泉徴収の徴収金額は、顧問料によって異なります。
100万円以下の部分に対しては、1回の支払金額の10.21%が源泉徴収額となります。100万円を超える部分に対しては、倍の20.42%が源泉徴収額です。
源泉徴収した所得税は、税務署へ納付します。原則として支払った月の翌月10日までに納付する義務があります。
原則は毎月締、翌月10日までの支払いですが、源泉徴収税の納付には特例があります(一般的にはほとんどの事業者がこの特例を活用しています)。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署へ提出することで、特例を受けることができます。
源泉徴収の納付に関する特例とは具体的には以下の通りです。
給与の支給人員が常時10人未満の場合は、半年分まとめて納めることができます。その年の1月から6月までの源泉徴収した所得税などは7月10日に、7月から12月に源泉徴収した分は翌年の1月20日が納付期限になります。
本来毎月源泉徴収を計算して納付する義務があるものが、半年毎になるわけです。経理事務作業の負担軽減になりますので、特例の申請をしておいたほうがいいでしょう。
税理士顧問料の仕訳方法、勘定科目はどうしたらいいのか
税理士へ顧問料を支払った際の仕訳は、借方を「支払手数料」、貸方は「普通預金」や「現金」などとして、その金額を記入するのが一般的です。
仕訳方法は、源泉徴収がある場合とない場合で異なります。
源泉徴収がない場合は、借方「支払手数料」、貸方「普通預金」や「現金」などとして、その金額を記入します。支払った額面通りの貸借一致になります。
次に源泉徴収ありの場合の仕訳です。
借方に「支払手数料」と金額を記入するのは、源泉徴収無しの場合と同様です。異なるのは貸方科目です。
「当座預金」や「普通預金」などとして金額を記入しますが、その金額は源泉徴収額を除いた金額となります。源泉徴収なしだと支払った額面でよいところが、源泉徴収額を区分して処理する必要が出てくるわけです。
源泉徴収する金額は、貸方へ「預り金」としてその金額を記入します。
また、顧問料が100万円を超える場合は計算方法にも注意してください。
先にご説明した通り、100万円以下の部分に対しては、1回の支払金額の10.21%が源泉徴収額となります。100万円を超える部分に対しては、倍の20.42%が源泉徴収額です。
(一般的に売上2,000万円以下の個人事業主の場合、税理士顧問料は月額2~3万円程度ですから顧問料が100万円を超えることはあまりありません)。
最後に、源泉徴収をした報酬があればいわゆる「支払調書」を作成して、税務署へ提出する必要があります。
外注費として支払った報酬について「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」という文書を作らなければ経費として認められないのです。
源泉徴収や仕訳について、ちょっと長くご説明してきたのですが経理処理が少々煩雑な分野になります。ご心配な点は所轄の税務署や税理士へ相談してみてください。
以上、税理士を雇うことについて周辺事情を簡単にご説明してきました。確かに源泉徴収はちょっとひと手間かかりますが、それ以上に顧問税理士がついてもらうことの大きなメリットはご理解いただけましたでしょうか。
ご自身の事業をみて、経理処理の省力化・適正化・顧問契約で得られるメリットを考えてみて年間顧問料で割に合うと判断されたら是非、税理士さんを雇っていることを考えてみてください。
iDeCo・ふるさと納税・仮想通貨の申告に対応、個人事業主・会社員の副業でも使えるおすすめ会計ソフト
-
個人事業主の銀行口座・屋号(開閉)
-
請求書未経験者のための作り方・送付方法(開閉)
-
個人事業主の節税(開閉)
-
ふるさと納税(開閉)
-
仮想通貨の確定申告(税理士執筆)(開閉)
-
e-tax(電子申告)について(開閉)
-
クラウド会計ソフトfreeeについて(開閉)
-
フリーランスと保育園(開閉)