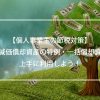短期前払費用の特例を利用しよう!【個人事業主の節税対策】

個人事業主が利用できる節税対策の中で、本来は今期の経費に算入できない前払費用を計上できる特例があります。今回はこの「短期前払費用の特例」について詳しく説明します。

【個人事業主の節税対策】短期前払費用の特例を利用しよう!
1 短期前払費用の特例とは
前払費用とは、「法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するもの」です(出典:国税庁HP)。
これは保険料や家賃のように、前もって代金を支払うことで効力が発生する費用をあらわします。また費用とはありますが、経過勘定項目の資産になります。
通常は決算年度をまたいで継続する契約における支払いを一括で行った場合、今期に役務の提供を受ける分と翌期に提供を受ける分とを分けておきます。そして翌期の分は今期の資産として計上し、翌期に損金(つまり経費)に振り替えることになります。
しかし、その翌期の損金も資産としてではなく、今期の損金に計上できるのが、「短期前払費用の特例」です。
2 通常の前払の処理方法と特例の違い
たとえば1年ごとに更新するリース契約の代金を支払うとします。金額は12万円、今期の分は3万円で翌期の分は9万円であると仮定します。
- 支払い時の仕訳
- 借方 賃借料 30,000
- 前払費用 90,000
- 貸方 普通預金 120,000
- 翌期の振替処理
- 借方 賃借料 90,000
- 貸方 前払費用 90,000
このように今期と翌期とを分けて処理します。今期はあくまでも前払費用という資産の科目で処理をしておいて、翌期の期首で振替処理をするというわけです。
当然ですが翌期の分は翌期の経費となります。支払いは今期に終えていますが、今期に役務の提供を受けていない分は今期の経費にはできません。
しかし翌期に提供を受ける役務の分も、今期の経費にすることが可能です。それが、「短期前払費用の特例」です。
この場合、上記の処理は以下のようになります。
- 支払い時の処理
- 借方 賃貸料 120,000
- 貸方 普通預金 120,000
この特例が認められるのは、継続して毎年サービスを受けるもの、という条件があります。
たとえば先の例で、今期は30,000円を経費として計上し翌期に90,000円を計上しています。そしてその翌期にも同じように30,000円を計上して、さらにその翌期に90,000円を計上します。すると翌期を見てみると、
- 30,000円+90,000=120,000円
を結果的に計上することになります。であれば、わざわざ手間をかけて会計年度をまたいで分ける必要もないのでは、となるわけです。これが数年間続くのであれば、その間は節税効果はまったく変わりません。
つまり節税効果が高まるという意味で効果があるのは、初年度の処理のみということです。
3 短期前払費用の特例に適用される費用とは
短期前払費用の特例に適用できるのは、継続的にサービスを受けるものだけです。そのため、対象となるものは限定されます。たとえば次のようなものが挙げられます。
- 地代家賃
- 賃借料
- 保険料
- 借入金利息
- 保守点検料
- 会費
つまり、先払い契約となる費用が適用対象になるということです。ただし、この特例が適用されるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
4 短期前払費用の特例が適用される条件
短期前払費用の特例が認められる条件として、次のような項目をすべて満たすことが必要です。
- ① 支払いから1年以内にサービスを受ける
- ② 毎年継続してサービスを受ける
- ③ 収益計上と対応させるものではない
(有価証券や定期預金運用のための借入金利息は対象外) - ④ 受ける役務の内容は等質等量でなければならない
①については少し説明が必要でしょう。たとえば4月1日から翌年3月31日までに受けるサービスの費用を2月に支払うとすると、そのサービスを受け終えるのは1年以内に収まらないので、短期前払費用の特例対象にはなりません。
この場合は3月に一括支払いをするように契約を結んでおくべきです。ただしサービス提供が3月31日までだからといって、支払いもきっちりと1年前の3月31日にする必要はありません。同月の3月のうちに支払いを済ませれば、問題はないということです。
さらに支払ったサービスが1年以上継続して受けるものであれば、短期前払費用の特例に適用することはできません。あくまでもそれぞれの年度で計算し経費計上する必要があります。
④についてですが、これは毎月同じ質・同じ量のサービス内容でなければならないということです。
たとえば弁護士や税理士の顧問料の場合、毎月同額の料金が発生するとしても、必要な時に相談したり代行サービスを受けるので対象外となります。あるいは雑誌広告料なども、雑誌が発刊されるタイミングで掲載サービスを受けることになるため、特例の対象外となってしまいます。
5 短期前払費用の特例における注意点
それでは短期前払費用の特例を利用するにあたり、注意すべき点を説明します。
5-1 月払い契約を年払いにするためには、事前に契約変更をしておくこと
短期前払費用の特例は、契約上で年払いを条件としているサービスしか適用されません。たまたま今期は利益が多く出たので、翌期の分をまとめて1年分支払ったとしても、それは特例として認められません。
もしまとめて支払うのであれば、事前に支払い条件を年払いとする旨、変更契約を締結しておく必要があります。
また翌期以降は毎年継続して年払いにしなければならないので、注意しましょう。その分負担も増える可能性があるからです。
5-2 節税効果が高いのは最初の年度のみ
短期前払費用の特例で節税効果が高まるのは初年度のみです。翌期以降は毎年、変わらずに1年分の支払い金額を経費計上するので節税効果は変わりません。また契約を終了する時は、最終年度の節税ができない点にも注意が必要です。
まとめ
短期前払費用の特例は申告する年度しか節税効果はありません。翌期以降は節税にはなりませんが、継続して受けているサービスがあり、利益が多くなりそうであれば今期の申告で利用してみてもよいのではないでしょうか。
参考サイト
「No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
iDeCo・ふるさと納税・仮想通貨の申告に対応、個人事業主・会社員の副業でも使えるおすすめ会計ソフト
-
個人事業主の銀行口座・屋号(開閉)
-
請求書未経験者のための作り方・送付方法(開閉)
-
個人事業主の節税(開閉)
-
ふるさと納税(開閉)
-
仮想通貨の確定申告(税理士執筆)(開閉)
-
e-tax(電子申告)について(開閉)
-
クラウド会計ソフトfreeeについて(開閉)
-
フリーランスと保育園(開閉)