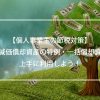保険を活用しよう!【個人事業主の節税対策】
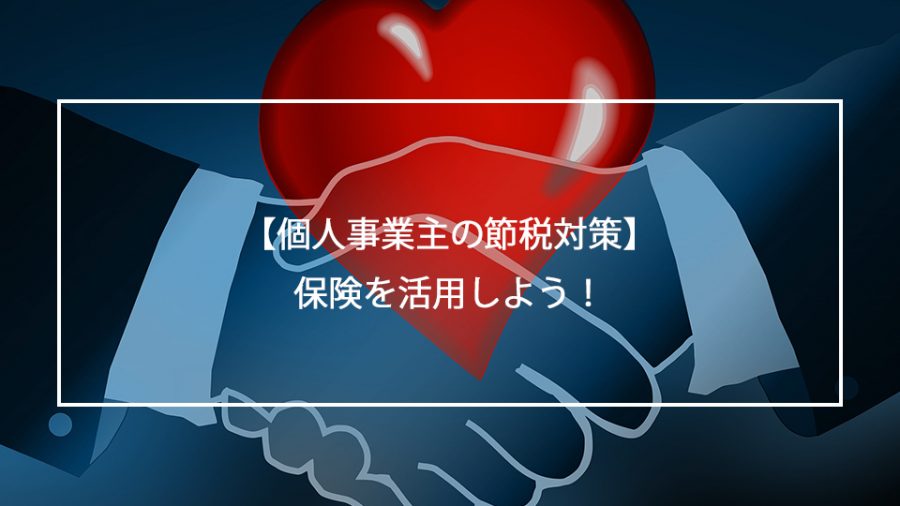
個人事業主のための節税対策として、ふたつの保険をご紹介します。ひとつは取引先の倒産に備えた保険で、もうひとつは退職金として役に立つものです。節税効果も高いので、ぜひチェックしてみてください。

【個人事業主の節税対策】保険を活用しよう
1 【節税に活用できる保険その1】中小企業倒産防止共済掛金
まず取引先の倒産によるリスク回避の保険をご紹介します。
1-1 個人事業主が経費にできる保険料とは
個人事業主は事業と関係のある保険料であれば、経費として申告できます。たとえば次のようなものがあります。
- 火災保険
- 自動車保険
- 自賠責保険
これらのうち、事業にかかわる分は経費として申告できます。自動車は個人として使用する分と事業のために使用する分とで按分して、その割合に応じた金額を計上します。
これらのほかにも経費として計上できる保険があります。「中小企業倒産防止共済掛金」です。
1-2 「中小企業倒産防止共済掛金」とはどんな制度なのか
中小企業倒産防止共済掛金とは、経営セーフティ共済とも呼ばれるものですが、独立行政法人中小企業基盤整備機構(略称;中小機構)というところが運営している制度です。
この制度の目的は、「取引先事業者が倒産した時に、連鎖倒産したり経営難に陥ったりすることを防ぐ」ことです。その仕組みは、取引先が倒産したことにより売掛金債権の回収が困難になった時、共済金の貸付を無担保・無保証人で受けられるというものです。
さらに取引先の倒産が原因ではなくても、臨時で資金が必要になった時にも掛金の範囲内で一時貸付金の貸付を受けることもできます。そしてその掛金は、個人事業主であれば必要経費に算入できることが、大きな特徴となります。
なお、中小企業庁発表による株式会社東京商工リサーチの調査結果での、中小企業の連鎖倒産件数は以下のとおりです。
- 平成24年 712件
- 平成25年 612件
- 平成26年 555件
- 平成27年 553件
- 平成28年 254件
- 平成29年 447件
- 平成30年 374件
1-3 独立行政法人 中小企業基盤整備機構とは
独立行政法人中小企業基盤整備機構場は、「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」の定めにより平成16年7月に設立された独立法人です。
中小企業やベンチャー企業などの事業者へ助言したり研修を行ったりしています。あるいは中小企業者向けに高度化融資や小規模企業共済などを提供しています。
1-4 掛金全額を経費にできるのがメリット
連鎖倒産は年々減少していますが、個人事業主としては無視できないリスクと言えます。そしてこの中小企業倒産防止共済掛金のメリットは、掛金のすべてを経費にできることです。
保険は大抵の場合、控除できる金額は全額ではなく一部となっています。ちなみにその理由としては、たとえば生命保険は普及率が高く、税制面における支援の必要性が問われていることが背景にあります。健康保険や年金の所得税控除も、廃止すべしとの意見も出ています。
(参考: 所得税における所得控除と税額控除のあり方について)
逆に言えば、この中小企業倒産防止共済掛金が全額経費と認められるのは、中小企業の連鎖倒産が看過できないものであると認識されているためと考えられます。
なお、事業における収入から経費として差し引くので、個人事業税の節税につながります。
1-5 掛金と共済金の貸付けについて
中小企業倒産防止共済掛金は倒産を回避するための貸付制度であることは説明しました。そのほかの詳しい内容についてご紹介します。
まず掛金ですが、月額掛金は5,000円から20万円の範囲内で、500円単位で選べます。借入れの上限は掛金の最大10倍(上限8,000万円)までか、あるいは回収困難となった売掛金債権などの額のうち、少ないほうです。掛金は自由に増減額できます。
共済金の返済期間は、6ヵ月の措置期間を含み借入額によって決まっています。
- 5,000万円未満 5年
- 6,500万円未満 6年
- 8,000万円以下 7年
利率は無利子ですが、借入後は共済金借入額の10分の1相当額が払い込んだ掛金から控除さらます。これはのちに受け取る解約手当金に反映されます。
1-6 「夜逃げ」は倒産とは認められない
共済金の借入れを申請するためには、取引先事業者の倒産が条件となります。この「倒産」の定義ですが、以下の7つが該当し「夜逃げ」は対象外なので注意が必要です。
- ・法的整理
- ・取引停止処分
- ・でんさいネットの取引停止処分
- ・私的整理
- ・災害による不渡り
- ・災害によるでんさいの支払不能
- ・特定非常災害による支払不能
1-7 解約手当金について
任意解約をすると、掛金の納付月数と掛金総額に応じて解約手当金を受け取れます。納付月数によって、以下の割合で掛金が戻ってきます。
- 12ヵ月未満 なし
- 23ヵ月以下 80%
- 29ヵ月以下 85%
- 35ヵ月以下 90%
- 39ヵ月以下 95%
- 40ヵ月以上 100%
つまり、経費として事業税を節税できるうえに、その掛金はあとで返金されるのでお得な制度と言えます。
1-8 必要経費算入の方法
掛金を必要経費に算入するためには、任意の用紙で『中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書』というものを作成し、確定申告に添付して提出します。
(参考サイト: http://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/faq/other.html)
2 【節税に活用できる保険その2】小規模企業共済等掛金
続いては、会社勤めをしていない個人事業主でも退職金を受け取れる制度をご紹介します。
2-1 小規模企業共済等掛金の概要
小規模企業共済等掛金も独立行政法人中小企業基盤整備機構が提供している制度です。個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度となります。
こちらは個人の収入から支払うものなので、事業の経費ではなく個人の課税所得から掛金すべてを控除することができます。そのため個人事業税は変わりません。
2-2 掛金の支払いと満期について
月額掛金は1,000円から7万円まで、500円単位で選べます。途中で増減額が可能なので、適時見直すとよいでしょう。掛金の納付は、月払い・半年払い・年払いのいずれかを選択します。前納すれば、一定割合の前納減額金を受け取ることができます。
共済金は退職・廃業時あるいは任意解約時に受け取ることができます。満期や満額といったものはありません。個人事業を廃止した時点で終了する仕組みとなります。
2-3 共済金の受け取り
共済金は共済を解約することで、解約手当金として受け取ります。
途中解約による解約手当金は、掛金納付月数が240ヵ月未満の場合、掛金合計額を下回ります。
任意解約ではない形として、3種類の共済金があります。個人事業を廃業した場合は共済金A、65歳以上で180ヵ月以上掛金を払い込んだ老齢給付は共済金B、個人事業を法人成りして加入資格がなくなった場合は準共済金となりす。それぞれ共済金の額は違います。
たとえば掛金月額1万円で掛金納付年数が5年の場合、共済金は次のようになります(掛金合計額600,000円)。
- 共済金A 621,400円
- 共済金B 614,600円
- 準共済金 600,000円
共済金の受け取りは一括あるいは分割、もしくはその併用から選べます。一括で受け取れば退職所得控除額を、分割であれば公的年金控除額を収入から差し引くこともできます。
共済金として退職金を受け取れるうえに、その掛金をすべて課税所得から控除できるとあって、お得な制度であると言えます。
まとめ
今回ご紹介した中小企業倒産防止共済掛金は個人事業税の節税に、小規模企業共済等掛金は個人の所得税と住民税の節税に役立ちます。
前者は任意解約手当金を、後者は退職金として共済金を受け取れるので、お得な制度と言えます。個人事業主の方は節税対策のためにも、検討してみてはいかがでしょうか。
参考サイト
「中小企業倒産防止共済制度の現状について」
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/2018/181126haifu03.pdf
「中小企業倒産防止共済制度の今後のあり方について(案)
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/2017/170301haifu03A.pdf
「原因別倒産件数」https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/tousan/190617bankruptcy.xls
「所得税における所得控除と税額控除のあり方について」
http://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/nichizeiren/business/taxcouncil/toushin_H21.pdf
「共済金について」
http://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/about/proceed/index.html
「解約手当金について」
http://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/about/loan/index.html#rates
「小規模企業共済」
http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/features/index.html
iDeCo・ふるさと納税・仮想通貨の申告に対応、個人事業主・会社員の副業でも使えるおすすめ会計ソフト
-
個人事業主の銀行口座・屋号(開閉)
-
請求書未経験者のための作り方・送付方法(開閉)
-
個人事業主の節税(開閉)
-
ふるさと納税(開閉)
-
仮想通貨の確定申告(税理士執筆)(開閉)
-
e-tax(電子申告)について(開閉)
-
クラウド会計ソフトfreeeについて(開閉)
-
フリーランスと保育園(開閉)